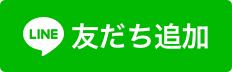「“いい子”より“考える子”を育てる」——工藤勇一先生が語る“主体性”の本質【前編】
「うちの子、やればできるはずなのに…」「言われないと動かなくて不安」——そんな気持ち、ありませんか?
本記事は、FC今治高校 里山校対談イベントで、横浜創英中学・高等学校 元校長 工藤勇一先生が語られた内容をもとに、子どもが自ら考え、動き出すために必要な主体性とは何かを、保護者目線でわかりやすく整理した特集の前編です。
1. 「自主性」と「主体性」は似て非なるもの
まず押さえたいのは、“自主性”と“主体性”は同じではない、という事実。工藤先生は次のように明確に区別します。
| 項目 | 自主性 | 主体性 |
|---|---|---|
| 定義 | 大人が望むことを自ら進んで行う力 | 言われたことでも一度立ち止まり、自分の頭で考えて判断する力 |
| 典型行動 | 「はい!」と即実行、期待に応える | 「なぜ必要?」「他の方法は?」と問い、納得してから動く |
| 周囲からの見え方 | “扱いやすい良い子” | ときに“面倒”に見えるが、意思と根拠を重視 |
ヨーロッパの育成年代は「腹筋100回」と言われてもすぐ動かず、効果や目的を質問してから着手するそうです。これは主体性の表れ。一方、日本では即実行が称賛されがちで、結果として「考えない習慣」を招くこともあります。
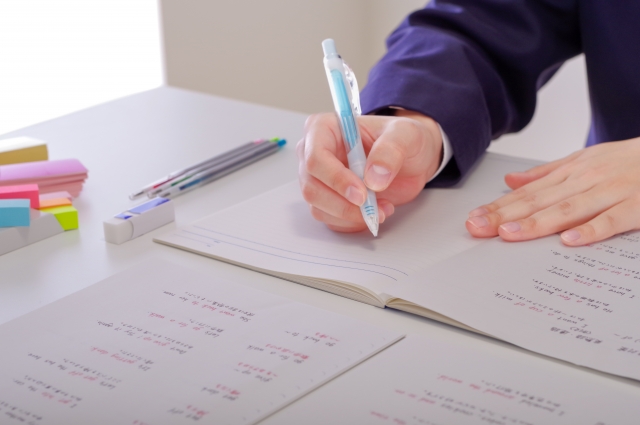
2. 生まれ持った「主体性」が消えていく理由
赤ちゃんは好奇心のかたまり。登る・試す・失敗する——すべてが“主体性”の原点です。では、なぜ成長とともに薄れてしまうのでしょうか。
原因① 「良かれと思って」の過干渉
「危ないからやめて」「こうしなさい」——愛情からの声かけが続くと、子どもは「失敗はよくない」「聞かれる前に正解を出そう」と学び、挑戦を避けるようになります。
原因② 失敗体験の不足
つまずき・試行錯誤・やり直しは、自己効力感(自分はできるという感覚)を育てます。失敗の機会が奪われると、「言われたことだけやる」へ収束しがちです。
原因③ 他責化のクセ
自分で決める経験が少ないと、うまくいかない理由を外側に求めがち。「先生のせい」「親が強く言うから」など、主体的な振り返りが育ちにくくなります。
工藤勇一先生(横浜創英中学・高等学校 元校長)講演より
「主体性は誰もが生まれつき持っている力。
しかし、過度の先回りや口出しが続くと、わずか数年で臆病になってしまう。」
朗報もあります。主体性は“ゼロになる”わけではありません。関わり方を変えれば、再び引き出せます。
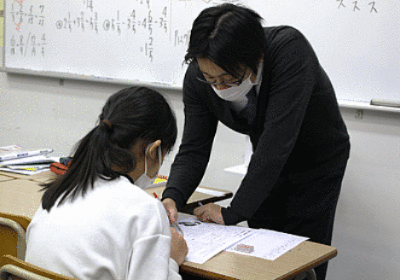
次回予告
後編では、すぐ実践できる「魔法の声がけ」3選と、なぜ今この時代に主体性が不可欠なのかを解説。保護者が「マネージャー」から「コーチ」へとシフトする具体策をお届けします。
▶ 後編はこちら:
===============
学習塾ComPass
松山市来住町230-1
豚太郎11号店さんそば
===============
学習塾ComPassは松山市の久米・南第二校区の生徒対象の学習塾です。
当塾では、子どもが主体的に動いていくための親子コミュニケーションのコツを保護者の皆様にお伝えしています。
小学生はいつでもウェルカムですので、ぜひ授業をご体験くださいね。
中学生は定期テスト後など、体験できる日程に限りがありますので、一度LINEにてお問い合わせください。
(2025年11月現在、中2のみ募集(残席1))
塾探しはまだ…って方も、
お得な学習情報の発信をしてますので、
公式LINEを友だち追加してみてください!